【中小企業の銀行対策】取引金融機関へのリスケジュール要請への心得とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関へのリスケジュール要請に際して、心得ておくべきことについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 リスケは事業継続を最優先させるための最後の砦である
2 リスケはできるがペナルティも大きい
どうぞ、ご一読下さい。
1 リスケは事業継続を最優先させるための最後の砦である
中小企業にとって、リスケジュールが身近な存在になったは、2009年に施行された中小企業金融円滑化法です。
同法は、2013年に期限切れとなってしまいましたが、金融機関の所管官庁が「債務者からの返済の条件変更には柔軟に対応すること」という行政指導が継続されていることで、よほどの事情がない限り、債務者中小企業が取引金融機関にリスケジュールを要請すれば、金融機関側が謝絶するというケースは極めて稀です。
金融機関が債務者からのリスケジュールを謝絶する例としては、例えば、反社との付き合いが顕在化したり、とか、著しい法令違反があったり(刑事事件になっているとかいうレベル)、とか、見るに堪えられないような粉飾決算を行なっていたり、とか、そういう特殊な事情が想定されます。
逆に、リスケジュールを中小企業経営者が躊躇したばかりに、金融機関への返済を優先したことで、消費税や社会保険料といった租税公課を滞納してしまったり、一般債権者への支払に遅延が発生してしまって仕入に支障が出たり、外注先への支払が滞って業界内で信用不安が囁かれてたりすれば、事業継続に支障が出ても不思議ではありません。
仕入先や外注先への支払が送れるようになると、社員の耳にも、会社の信用不安が入ってくるようになります。
「うちの会社、やばそう。もう長くはないな」とお昼休みの休憩室で、求人情報誌が回し読みされるようなことになれば、社内の士気は低下し、業況はますます悪化してしまうかもしれません。
確かに、真面目な経営者ほど、「今までお世話になってきた銀行に迷惑をかけるわけにはいかない」とリスケジュールを先送りするケースがなきにしもあらずです。
消費税や社会保険料は預かり金としての性格が強いため、一度租税効果を滞納してしまうと、発生する租税公課を通常に納付しながら滞納分を併せて納付しなければならなくなるので、ますます資金繰り余力を削いでしまいます。
このように、支払の優先順位を間違うことなく、リスケジュールは事業継続を最優先するための最後の砦であることを経営者は改めて認識しなければならないのです。
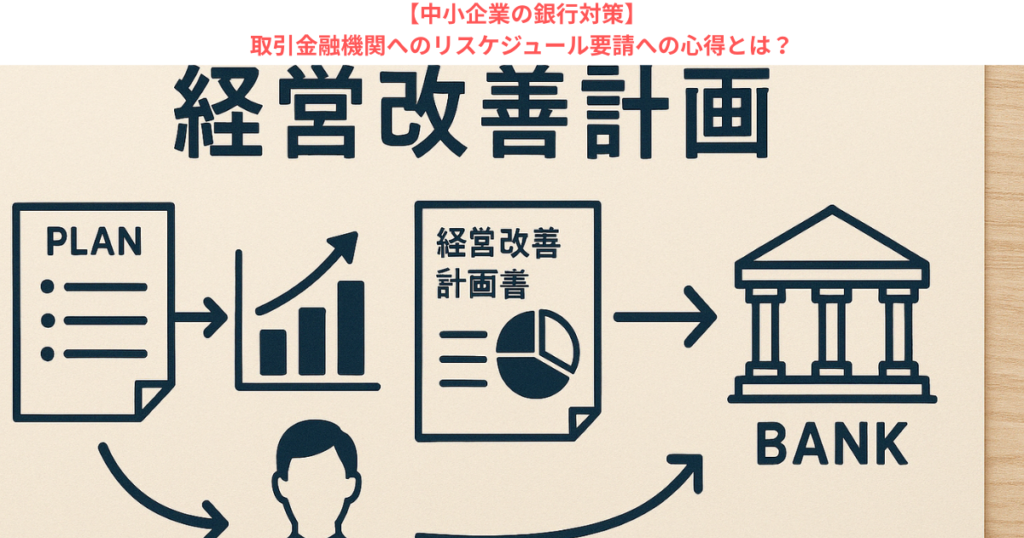
2 リスケはできるがペナルティも大きい
中小企業がリスケジュールに踏み切らざるを得ない背景として、コロナ禍後の物価高が挙げられます。
コロナ禍が明けて世の中が正常に戻っていく中で、ありとあらゆる物価が上がり、中小企業の原価高と諸経費負担増が、中小企業の収益圧迫要因となっています。
加えて、資金調達したコロナ資金とその借換資金が昨年6月末で期限切れとなったことで、コロナ資金の折り返しが効かず、コロナ資金は返済する一辺倒になっていて、資金調達難となっていることも見逃せません。
そのような中、事業継続を最優先とするためのリスケジュールは合理的なものではあります。
上記でも申しましたが、経営者の中には、「意外と大したことないんやな」と感じている方がいるかもしれません。
確かに、リスケは入り口は楽勝なのですが、問題は出口が厄介なことです。
リスケジュールによって、言ってみれば、出血が止まるので、経営者は一種、安心してしまう傾向があります。
しかしながら、リスケジュールした借入金は、どこまでいっても借入金なので、どこかでちゃんと返済していかなければなりません。
補助金や助成金と違って、借りたカネは返さなければならないのです。
このため、リスケジュール後には、アクションプランとそれに対応した収益計画を骨子とした経営改善計画を策定して、その計画をしっかりと履行していくことが必須です。
そして、収益を改善して、傷んだBSを実質ベースで健全化させ、最長10年間でリフィナンスするというゴールに向かって、経営改善計画を実りあるものにする必要があります。
もちろん、リスケジュール後は、原則として、ニューマネーの調達はできなくなるので、その意味では経常損益での赤字幅は減価償却費の範囲内に収まっていくはずです。
このように、リスケジュールは入り口はユルユルですが、出口はなかなかの険しさです。
中小企業経営者がリスケジュールを正しく理解することで、リスケジュールをいい意味で恐るべき存在することができるのです。

