【中小企業の銀行対策】コロナ借換保証終了から1年経過した今経営者が心得ておくべきこととは?
今日は、中小企業の銀行対策として、コロナ借換保証終了から1年経過した今経営者が心得ておくべきことについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 コロナ借換保証は返済一辺倒である
2 据置期間が長ければ長いほど返済負担は増す
どうぞ、ご一読下さい。
1 コロナ借換保証は返済一辺倒である
思い返せば、2020年、横浜のクルーズ船に端を発した新型コロナウイルス感染症は、あっという間に日本全国に拡大し、サービス業を中心に商いをしたくてもできない事実上のロックダウンの状態となり、サービス業等の中小企業の資金繰りは一気に悪化しました。
中小サービス業の事業継続を優先させるため、サービス業に限らず、多くの中小企業がコロナ資金で資金を調達しました。
そんな新型コロナウイルス感染症もようやく終息に向かい、コロナ資金の借換保証制度も2024年6月末受付分で終了しました。
2024年6月末にかけて、多くの中小企業が既存のコロナ資金を折り返して借りる借換保証を利用し、資金調達に奔走しました。
コロナ借換保証は、保証料の補助を受けることができたため、補助後の実質的な信用保証料は0.2%と格安でした。
また、元本返済も最大5年据え置くことができるなど、破格の条件と言えました。
コロナ借換保証終了からちょうど1年が経過した今、どのようなことが起こっているのか、考えてみることにします。
コロナ借換保証の終了によって、文字通り、借換が終了したため、返済分の折り返しが効かなくなりました。
つまり、1年前に調達したコロナ借換保証の借入は、ひたすら返済していくだけということになっています。
返済期間が10年となっているため、返済負担は比較的軽いのですが、返済負担が軽いということは、元本がなかなか減らないということです。
2024年6月、期限ギリギリで調達したコロナ借換保証の完済時期は実に2034年6月、今から9年後ということになります。
実に長丁場で、気の遠くなるようなお話です。
コロナ資金と借換保証は、調達する時は「アメ」そのものでしたが、返済が長期にわたるため、返済については「ムチ」ということができるかもしれません。
いずれにしても、コロナ借換保証によって資金調達した中小企業にとっては、コロナ借換保証の資金とは長い長い付き合いということになってしまうのです。
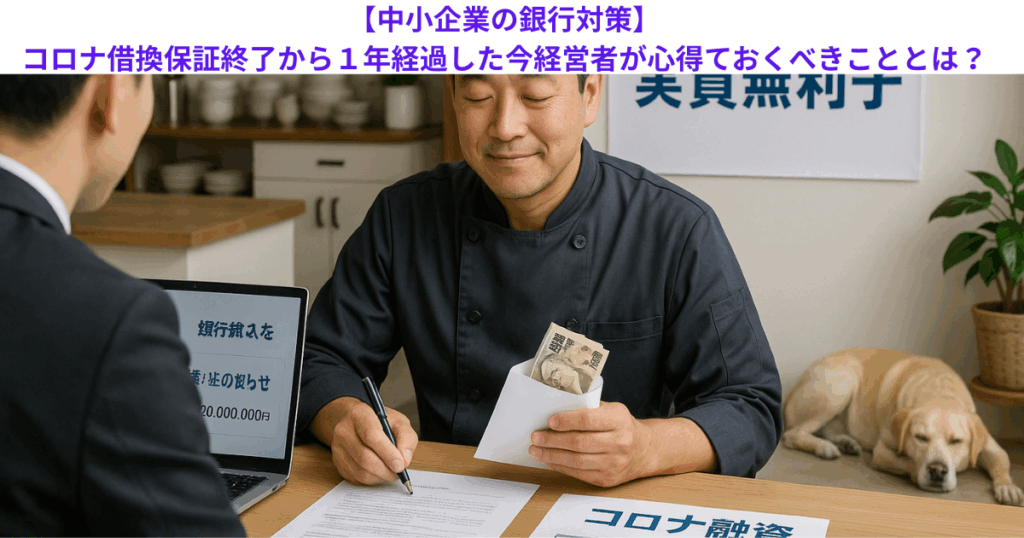
2 据置期間が長ければ長いほど返済負担は増す
コロナ借換保証の特徴の一つが、元本返済に据置期間があることです。
期間10年は変わりませんが、元本据置期間は最大5年間まで設定することができました。
元本据置期間は利払いのみとなるので、資金繰り上は非常に有利なのですが、元本据置期間が長ければ長いほど、据置期間終了後、返済がスタートした後の返済負担は自ずと重たくなってしまいます。
例えば、調達金額50百万円の場合、据置期間がなければ、返済回数は120回で、月次元本返済額は417千円ですが、据置期間1年間の場合、返済回数108回で月次元本返済額463千円に増加し、据置期間5年間の場合、返済回数は60回なので、月次元本返済額が833千円にまで跳ね上がります。
困ったことに、コロナ終息後、原材料高、人手不足による人件費高騰、水光熱費や燃料費の上昇といった想定外のコストアップが常態化してしまったことで、業種、業態を問わず、中小企業の経営を巡る外部環境は厳しさを増す一方です。
据置期間1年間の場合、既に、据置期間が終了し、元本返済がスタートしてきます。
コストアップによって、十分なキャッシュフローを創出できないとなると、元本返済に耐え切れず、元本返済開始後間もなくリスケジュールに踏み切らざるを得なくなる中小企業が出てくる可能性は高まる一方です。
中小企業経営者は、いわゆる損益分岐点をベンチマークにするのではなく、元本返済額を加味したキャッシュフロー創出するために必要な収益を確保していく必要があるのです。

