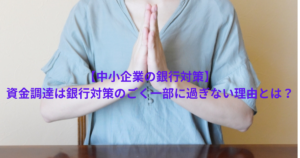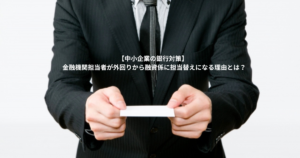【中小企業の銀行対策】現預金確保から次の成長に現預金を振り向けていく必要性とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、現預金確保から次の成長に振り向けて現預金を振り向けていく必要性について考えます。
今日の論点は、以下の2点。
1 現預金確保の非常事態モードは終了した
2 現預金を次の成長に振り向けていく
どうぞ、ご一読下さい。
1 現預金確保の非常事態モードは終了した
新型コロナウイルス感染症の感染症区分が、2類から5塁に引き下げられてから1年超が経過しました。
世の中はすっかりアフターコロナの様相で、インバウンドを中心に、人々の流れはコロナ前に回帰したと言えそうです。
この流れを受けて、行政によるコロナ対策も縮小の一途で、金融面での象徴であったコロナ資金(現状運用されている伴走型資金)もこの6月末で、信用保証協会の受付が終了します。
伴走型資金の終了を前に、各地の信用保証協会は、伴走型資金の申し込みが殺到していて、パンク状態を呈しているようです。
もはや、コロナ禍は、過去のものになってしまったと言っても差し障り無いような状況です。
他方、コロナ前には想像だにしなかったような円安の進行と、それに伴う原材料価格の上昇と人手不足は新たな中小企業にとっての脅威になっています。
このような局面の変化に中小企業であっても、なんらかの対応をして対策を講じなければなりません。
コロナ禍では、多くの中小企業がコロナ資金を調達して、手元流動性確保を最優先に重きを置きました。
とにかく、現預金を持っておけば、不測の事態に対処できると、中小企業経営者は危機感を募らせました。
このような非常時マインドを、中小企業経営者は払拭しなければなりません。
守りの姿勢から、攻めのスタンスへの転換をする局面が到来しているのです。
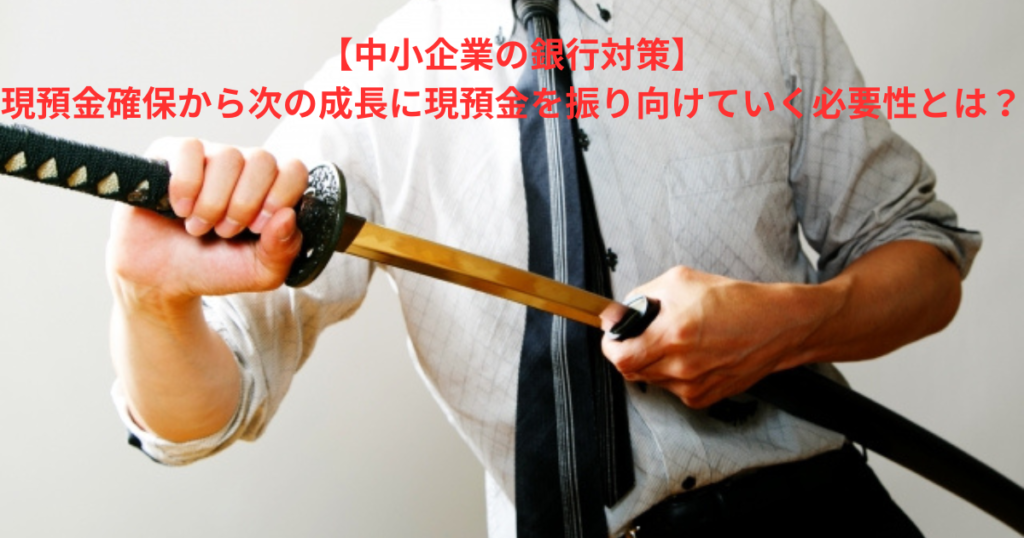
2 現預金を次の成長に振り向けていく
コロナ禍を経て、未だ、多くの中小企業経営者のマインドが「守り」のスタンスにあることは自然なことですが、だからと言って、安全志向を強めた結果、現預金を溜め込んでいては、資産のポートフォリオとしては決して効率的とは言えません。
上場企業であれば、必要以上に現預金を溜め込んでいると、株主から現預金を次の成長に振り向けるよう、株主提案で経営陣が吊し上げられますし、そもそも現預金が多過ぎる上場企業は、敵対的なTOBの対象になってしまいかねません。
非上場で、オーナー経営の中小企業であれば、株主=経営陣なので、株主からの圧力を受けることはありませんが、現預金ばかりを溜め込んでいること自体、会社の成長スピードを落としてしまうことは間違いありません。
現預金を次の成長に振り向けていくことが急務です。
積み上がった現預金の活用としては、まず、コロナ禍で返済をリスケジュールしている場合は、元本返済額の増額によって、有利子負債を圧縮して、リファイナンスへの距離を縮めることがまずもって重要です。
また、銀行返済が正常であれば、現預金を設備投資に振り向けることで、生産性の向上や省力化を図っていくことが肝要です。
7月以降、伴走型資金の制度がなくなるため、金融機関は融資の案件が落ち込んでしまうことが必至なので、設備投資案件があれば、一部自己資金で設備資金借入をメインバンクに要請すれば、「ぜひ、設備資金を当行で取り組ませて下さい」と前のめりになってくれることが期待されます。
また生産性の向上によって賃上げ原資を確保することができますし、優秀な社員を安定的に雇用し続けることもできます。
生産性を上げることによって、原材料単価の上昇分を吸収することも期待できます。
中小企業経営者は、2024年6月が終わりを告げるこのタイミングだからこそ、現預金を次の成長に繋げていけるよう、攻めの経営に転換する必要があるのです。